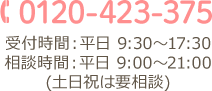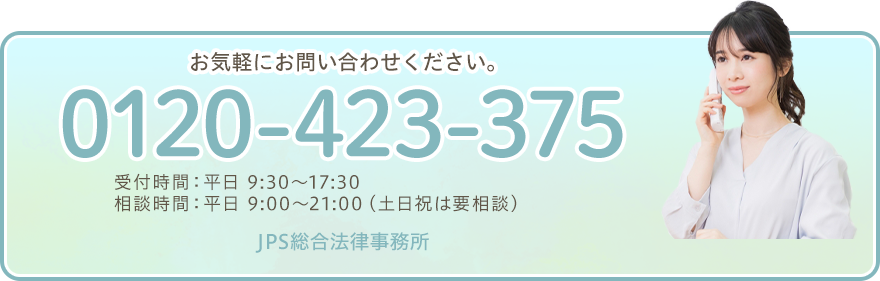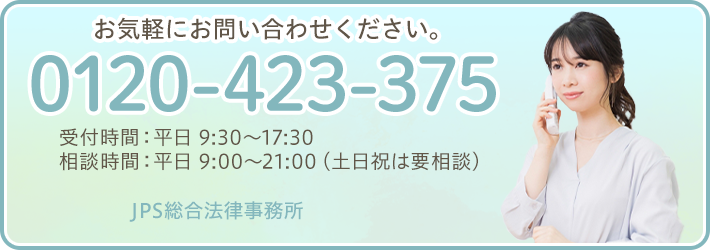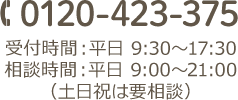面会交流に不安を感じる女性の方へ
離婚を考えている女性の方の中には、面会交流について不安な気持ちや、場合によっては戸惑い等を感じている方もいらっしゃいます。
共同親権という言葉も広まってきており、共同親権が面会交流にどのような影響を与えるのかということも踏まえ、面会交流に不安を覚える方もいらっしゃいます。
また、夫から、いわゆるDVやモラハラを受けてきた女性にとって、離婚後も子どもを通じて夫と関わり合いを持つことに具体的な不安を覚える女性の方、漠然としたイメージから、元夫との面会交流に抽象的な不安を覚える女性の方もいらっしゃいます。
この記事では、面会交流に対して不安や疑問を抱える女性の方に向けて、法律や裁判所での運用を踏まえつつも、少しでも、女性の方の心の不安を軽減するための、可能な限り具体的な方法をお伝えしようと思います。
面会交流とは何か?
そもそも、面会交流とは、離婚後に親権者とならなかった親が、子どもと直接会ったり、電話やビデオ通話などを通じて交流したりすることを指します。また、離婚に至らない段階でも、子どもと一緒に暮らしていない親が、子どもと上記のような交流を行うことを指します。
民法にも規定がありますし、裁判例や実務上も認められているものです。
面会交流の具体的な方法態様等については、第一次的には、親の目線ではなく、子どもの目線で考えることが重要となり、「子の福祉」を尊重して、決めることが望ましいとされております。
仮に、夫婦が離婚をしたとしても、元夫や元妻が、子どもにとっては親であることは変わりがありません。また、子どもにとっては、離婚は必ずしも望ましいものとは限らず、そのような親子の関係性を保ちつつ、子どもが健全で、なおかつ安心して成長することができるように、例外的な事情がない限り、面会交流が行われることとなっており、裁判所の立場も、このように解されていおります。
面会交流に不安を感じる理由
しかしながら、女性の立場に立つと、このような考えを説明すればするほど、女性が抱える不安が大きくなってしまうことが少なくありません。
例えば、夫から、いわゆるDVやモラハラを受けていた女性の方。
いくら、子どものためという説明をされたとしても、面会交流のために夫(元夫)とやり取りをすること自体、想像が及ばないほどの苦痛があります。精神的な不安も、計り知れません。
例えば、夫からのDVやモラハラを子どもが目撃しており、子どもも、夫(元夫)に対して恐怖を覚えていることもあります。
そのような中、気持ちの整理をせずに面会交流を強制することは、妻や女性だけではなく、子どもの立場に立ったとしても、好ましくない結果となることもあります。
女性のお気持ちの整理をしつつ、納得の上、面会交流を実現することが重要となってまいります。
その他、妻や女性の立場で、お子様の面会交流に対して不安を感じるポイントとして、以下の例があげられます。
夫や元夫からの精神的なプレッシャー
夫や元夫からのDVやモラハラの過去
子どもが会いたがっていない
夫や元夫の生活環境への不安
女性や妻の、新しい生活への影響
これらの不安は決して小さなものではありません。女性や妻が、特にDVやモラハラの被害者である場合、夫や元夫との接触を避けることが女性自身や子どもの心身を守るために重要となってくることも珍しくありません。
面会交流は子どもの発育の観点から重要だということはそのとおりなのですが、このような観点からも、慎重に考える必要があります。
例外的に面会交流を制限できるケース
すでにお話したとおり、面会交流は子どもの福祉を最優先に考慮する必要があります。このような観点から、次のような例外的なケースでは面会交流を制限できる可能性があります。
元夫によるDVや虐待の事実
子どもへの悪影響が懸念される場合
元夫が子どもを連れ去る危険がある場合
子ども自身が強く拒否している場合
このような事情がある場合は、家庭裁判所へ適切な主張を行うことで、面会交流を制限または中止できる可能性があります。
もっとも、裁判所のスタンスとしては、原則として、面会交流(このトピックでいう父子交流)を実現する方向にて手続きを進める方向にあります。
他方で、面会交流を行う上で女性や妻、元妻が抱える不安も理解することができます。不安がある場合は、一人で悩みを抱えることなく、面会交流の協議、調停、審判について経験豊富な弁護士にご相談されることをお勧めします。
事案によって対応は異なりますが、例えば調停手続きにおいて、裁判所は面会交流を実現する方向で、手続きを進める傾向にあります。他方で、伝え方にもよりけりですが、女性が抱える不安にも、一定程度配慮してくれることもあります。
不安な気持ちを、調停の場では、特に家庭裁判所調査官に対して説明をすることで、結果的に、面会交流に関するルールを作ることができ、面会交流を実現する際に、少しでも安心して進めることができる環境を作ることが、何よりも重要になるかと思われます。
面会交流における現実
上記のように、裁判所は基本的に、子どもの健全な成長にとって親子の関係を維持することが重要であると考えています。そのため、面会交流を全面的に拒否することは難しいのが現実です。
しかし、例えば、無理に面会交流を続けることが子どもにとって悪影響を及ぼすと判断された場合には、立ち会いの元で面会交流を行うことや、ビデオ通話を使った間接的な面会交流に限定されることもあります。
その他、面会交流の場所を提供してくれる第三者機関に間に入ってもらうことも、検討事項の一つとなります。
面会交流の条件を工夫する
面会交流を完全に回避することが難しい場合でも、以下のような方法で負担を軽減できます。
面会交流の頻度や時間を制限する
第三者機関を利用した面会交流を行う
子どもの心理的負担を最小限にする方法を検討する
相手の不適切な言動を防ぐために立ち会いを求める
調停や審判では、あなたの不安や懸念を丁寧に説明し、合理的な条件を求めることが重要です。
ただし、個別事情によって、対応は大きく異なります。
面会交流の調停や審判に精通した弁護士に相談されることをお勧め致します。
面会交流に関する具体的な条件の決め方
具体的な条件を決める際には、以下のような項目を考慮することが必要です。
回数・頻度:例えば、月に1回、数時間程度など、無理のない範囲で設定
実施場所:公共の場所や子どもの安心できる場所を指定
方法:対面交流に加え、電話やビデオ通話なども検討
受け渡し方法:親同士が直接顔を合わせないよう、第三者の立ち会いや施設を利用
また、子どもの体調不良や行事の予定などを考慮して、柔軟な決め方をするのか、それとも、面会交流に関するやり取りを必要最小限度に抑えるため、例えば、曜日や受け渡しの方法を固定して、決め事をすることも検討する必要があるかと思います。
面会交流の条件を守らないことへの対応
面会交流の条件に合意したにもかかわらず、夫や元夫が条件を守らない場合は、以下の方法で対応をすることが考えられます。
家庭裁判所への履行勧告:裁判所が夫や元夫に対して条件を守るよう促します。
調停の申し立て:新たに調停を申し立てて、話し合いを再開します。
間接強制の申し立て:一定の金銭を支払うよう命じることで、条件の履行を促します。
この内、揉め事が大きい場合は、再度、裁判所を通じた面会交流の調停にて、再度、話し合いを行うことが無難な場合もあります。
煩雑に見えるようですが、当事者同士で争い事が大きい分野でもあります。
再度の面会交流調停にて話し合うという選択肢も、頭の片隅に入れておければ、より柔軟に、安心した進め方をすることができる幅が広がると思慮致します。
弁護士に相談するメリット
すでにお話したように、面会交流に関する問題は、感情的な対立が激しくなりやすい分野です。
かといって、画一的な決まりがあるかというと、個別具体的な事情に応じて、具体的な進め方を調整する必要がございます。
そのような中、弁護士に依頼することで、以下のメリットがあります。
冷静で客観的なアドバイス
裁判所への適切な主張のサポート
心理的負担の軽減
当事務所では、女性や妻の方が安心して相談できる環境を整えています。あなたの気持ちを尊重しながら、法的なサポートを全力で提供します。お気軽にご相談ください。
あなたとお子さんのよりよい未来のために、一緒に最善の方法を考えるお手伝いができれば幸いです。